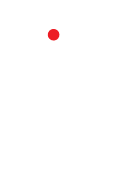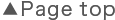協創の森・諸塚村
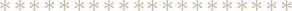
諸塚村は九州の屋根といわれる九州山脈の中に位置し、諸塚山を中心とする
標高1,000m級の山々に囲まれた人口1,500人ほどの自然豊かな村です。
「世界が認めた森」「シイタケの産地」
「針広照の3種の樹林が織りなす美しいモザイク林相」などで有名です。
森の特徴
 諸塚村は、平地が少ないゆえに昔から山林を活用して生活してきました。
そのため、昔から人工林率が高いのですが、土壌や地形等を考慮し、その土地に応じた樹種を選択するなど、
森の恵を持続可能にする工夫をして長い歴史を刻んできました。
諸塚村は、平地が少ないゆえに昔から山林を活用して生活してきました。
そのため、昔から人工林率が高いのですが、土壌や地形等を考慮し、その土地に応じた樹種を選択するなど、
森の恵を持続可能にする工夫をして長い歴史を刻んできました。
戦後全国的にスギ、ヒノキの一斉林が植えられる中で、針葉樹と広葉樹を7:3の割合で混植する施策をとりました。
その結果、諸塚の森全体が、針葉樹とクヌギやナラなどの広葉樹とが混洧する、美しい独特の景観を生み出しています。
新緑の時期や、紅葉の秋には、山々がモザイク模様に染まります。
クヌギは諸塚村の村の木となっており、特産のシイタケの原木として大切に育成されています。
また、村の活性化のための『クヌギの森』プロジェクトのシンボルともなっています。


森への取り組み
 諸塚村の先人達は焼畑、炭焼き、
シイタケ栽培をはじめとして古の昔から森の恵みを活かして生きてきました。
諸塚村の先人達は焼畑、炭焼き、
シイタケ栽培をはじめとして古の昔から森の恵みを活かして生きてきました。
この森を維持するべく、林業立村をスローガンに、山を守り、森林を創り、自然と共生しつつ、
森の恵みを受けながら村づくりを進めており、
全村森林公園を目指しています。
諸塚村は、第三者機関による森林認証取得にも村全体として積極的に取り組んでいます。
諸塚村が認証を受けたFSCは厳しい審査で知られてますが、環境問題と森づくりを融合させ、
他の模範となるような林業経営が認められました。

聴こえてくる鳥や動物たちの声
 メジロ、シジュウカラ、ヤマガラ、ウグイスが多く見られますが、春先から初夏にかけてはオオルリ、
ホトトギス、アオバトが盛んにさえずっています。
従来南西諸島に生息していたリュウキュウサンショウクイが、近年よくみかけるようになりました。
メジロ、シジュウカラ、ヤマガラ、ウグイスが多く見られますが、春先から初夏にかけてはオオルリ、
ホトトギス、アオバトが盛んにさえずっています。
従来南西諸島に生息していたリュウキュウサンショウクイが、近年よくみかけるようになりました。
野生動物では、イノシシ、シカが昔から生息していており、夜になると足音が聴こえることがあります。


四季折々の花や植物の彩り
 諸塚村東端にある最高峰の黒岳周辺では、希少な植物、キレンゲショウマをはじめとしてバライチゴ、バイケイソウ、
ウリノキ、キリンソウ、ナツハゼ、オオバノトンボソウ、クサタチバナなどが見られます。
諸塚村東端にある最高峰の黒岳周辺では、希少な植物、キレンゲショウマをはじめとしてバライチゴ、バイケイソウ、
ウリノキ、キリンソウ、ナツハゼ、オオバノトンボソウ、クサタチバナなどが見られます。
また、春先のフクジュソウは日本で群生する南限となっていたり、
バラ科の新種植物、モロツカウワミズサクラなどが発見されるなど、豊かな生態系が特徴です。